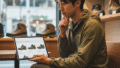小型船舶免許を取得して、憧れのクルーザーで大海原へ。そんな夢を描いているものの、具体的に何から始めれば良いのか、疑問や不安も多いのではないでしょうか。船舶免許の費用は一体いくらかかるのか、そもそも小型船舶免許で乗れるクルーザーとはどのようなものなのか、知りたいことは尽きないはずです。
また、2級船舶免許で乗れる船の値段や、航行できる範囲、例えば小型船舶1級で航行できる範囲はどこまでなのか、といった具体的な情報も気になるところです。新艇は高価なイメージがありますが、中古艇の価格相場を知れば、より現実的に購入を検討できるかもしれません。
しかし、所有にはメリットだけでなくデメリットも存在し、購入後の失敗や後悔を避けるためには、事前に全体像を把握することが大切です。いきなり購入するのはハードルが高いと感じる方のために、2級船舶免許で乗れる船のレンタルという選択肢もあります。
この記事では、総トン数20トン未満というクルーザーの大きさから、免許取得、船の選び方、そして維持費に至るまで、あなたの疑問を一つひとつ解消していきます。

イメージ画像
この記事を読むことで、あなたは次の4つの点を明確に理解できます。
|
―記事のポイント―
|

小型船舶免許で乗れるクルーザーの種類と選び方

イメージ画像
|
知っておきたい船舶免許の費用と種類
クルーザーを操船するためには、まず国家資格である小型船舶操縦士免許の取得が必要です。この免許にはいくつかの種類があり、それぞれ操船できる船の大きさや航行できる範囲、そして取得にかかる費用が異なります。ご自身の目的や遊び方に合った免許を選ぶことが、クルーザーライフの第一歩となります。
主な小型船舶免許の種類
一般的に、プレジャーボートやクルーザーの操船で対象となる免許は「1級」「2級」「特殊」の3つです。
-
1級小型船舶操縦士免許: 全ての海域を航行できます(一部制限あり)。長距離のクルージングや外洋での本格的な釣りを考えている方向けの最上級免許です。
-
2級小型船舶操縦士免許: 海岸から5海里(約9km)までの範囲を航行できます。沿岸での釣りや日帰りのクルージングを楽しむのに十分な免許で、最も一般的なものと考えられます。
-
特殊小型船舶操縦士免許: 水上オートバイ(ジェットスキー)専用の免許です。クルーザーの操船はできません。
この他に、湖や川のみで航行可能な「湖川小出力限定免許」もあります。乗船できる船の大きさ(総トン数20トン未満)は、1級も2級も同じです。
免許取得にかかる費用の目安
免許の取得費用は、教習所に通うか、独学で国家試験に臨むかで変わってきます。一般的には、講習から試験までが含まれる教習所を利用する方が多いです。
| 免許の種類 | 費用相場(教習所利用) |
|
1級小型船舶操縦士 |
約12万円 ~ 15万円 |
|
2級小型船舶操縦士 |
約10万円 ~ 13万円 |
|
特殊小型船舶操縦士 |
約6万円 ~ 8万円 |
これらの費用には、教習料、教材費、身体検査料、国家試験の受験・登録免許料などが含まれていることがほとんどです。ただし、教習所によって費用やプラン内容が異なるため、事前に詳細を確認することが大切です。すでに2級免許を持っている方が1級へステップアップするためのコースもあり、その場合はより安価に取得が可能です。
1級と2級で乗れる船の具体的な違い

イメージ画像
小型船舶免許の1級と2級、どちらを取得すべきか悩む方は少なくありません。乗船できる船の大きさは、前述の通り、どちらも「総トン数20トン未満」で同じです。したがって、免許の種類によってクルーザーのサイズが制限されることはありません。
では、最も大きな違いは何かと言うと、それは「航行区域」です。
| 免許の種類 | 航行区域 | 主な用途 |
|
1級小型船舶操縦士 |
すべての海域<br>(沿岸から100海里以上離れる場合は条件あり) |
外洋でのセーリング、長距離クルージング、トローリングなど |
|
2級小型船舶操縦士 |
平水区域および海岸から5海里(約9km)以内 |
沿岸での釣り、日帰りクルージング、ウェイクボードなど |
2級免許で十分楽しめるマリンライフ
2級免許で航行できる「5海里」という範囲は、陸地が見える距離であり、一般的なレジャーであればほとんどのケースをカバーできます。湾内でのクルージングや、少し沖に出て釣りを楽しむといった用途であれば、2級免許で全く問題ありません。全国のマリーナやレンタルボートの多くは、この5海里の範囲内で十分に楽しめるロケーションにあります。
1級免許が活きるシチュエーション
一方、1級免許の真価が発揮されるのは、より本格的なマリンアクティビティを目指す場合です。例えば、伊豆諸島への航海や、カジキを狙った外洋でのトローリング、あるいは隣県のマリーナまで数日かけてクルージングするといった壮大な計画には1級免許が不可欠です。将来的に大きな夢を描いているのであれば、最初から1級を取得しておくのも一つの選択肢と考えられます。
上限の20トンとは?クルーザーの大きさ
小型船舶免許で操船できる船の大きさの上限は「総トン数20トン未満」と定められています。しかし、「総トン数」と言われても、具体的にどれくらいのサイズの船なのかイメージが湧きにくいかもしれません。
ここで言う総トン数とは、重さではなく船の容積を示す指標です。実際の船の大きさは、一般的に「フィート(ft)」や全長(メートル)で表現されることが多く、こちらの方がサイズ感を掴みやすいです。1フィートは約30.48cmです。
総トン数20トン未満のクルーザーは、おおむね全長24メートル未満の船が該当します。これは非常に幅広く、比較的手軽なサイズのボートから、かなりの大型クルーザーまで含まれます。
サイズ別クルーザーの目安と用途
-
20~25フィート(約6m~7.5m):
エントリーモデルとして人気のあるサイズです。釣りやウェイクボードなど、アクティブなマリンスポーツに向いています。数人での日帰り利用がメインとなります。
-
26~35フィート(約8m~10.5m):
ファミリークルージングに最適なサイズ感です。キャビン(船室)やトイレ、簡単なキッチン設備が備わっているモデルも多く、船上での滞在が快適になります。仲間を招いてのパーティーにも対応できます。
-
36~50フィート(約11m~15m):
ラグジュアリーな空間を持つ大型クルーザーです。複数のベッドルームやシャワー、充実したキッチンを備え、船上泊も余裕でこなせます。長距離のクルージングにも適しており、まさに「洋上の別荘」と言えるでしょう。
このように、同じ免許で操船できる範囲の中でも、クルーザーの大きさによって楽しみ方は大きく広がります。
遠洋も可能?小型船舶1級で航行できる範囲は?

イメージ画像
1級小型船舶操縦士免許を取得すれば、航行区域の制限は「すべての海域」となります。理論上は、世界中の海へ航海することが可能です。しかし、これにはいくつかの現実的な条件と制約が伴うことを理解しておく必要があります。
最も大きな制約が、通称「100海里の壁」と呼ばれるものです。日本の沿岸から100海里(約185km)を超える海域を航行する場合、以下の条件を満たさなければなりません。
-
6級海技士(機関)以上の資格を持つ機関長を乗船させること
-
GPSやレーダーといった近代的な航海計器に加えて、六分儀(天体の位置を測定する古典的な航海用具)を船に備えること
これらの条件は、プロの船乗りでない限り、満たすのが非常に困難です。そのため、一般的なレジャー目的のクルージングでは、事実上、沿岸から100海里以内の範囲が行動の限界点となります。
しかし、100海里という範囲は非常に広大です。日本列島は海岸線が長いため、この範囲内であれば、北海道から沖縄まで、日本のほぼ全ての沿岸を航行できます。島々を巡る冒険的なクルージングや、大海原での本格的なフィッシングなど、2級免許では体験できないダイナミックな船旅を実現できるのが1級免許の最大の魅力です。
また、航行区域が無制限であっても、実際にどこまで行けるかは船の性能、特に燃料タンクの容量や耐航性に大きく左右されます。安全な航海計画を立てることが、何よりも大切になります。
新艇も!2級船舶免許で乗れる船の値段
クルーザーの購入を考えたとき、最も気になるのがその価格でしょう。2級船舶免許で乗れる船、つまり総トン数20トン未満のクルーザーの値段は、まさにピンからキリまで存在します。新艇の価格は、船のサイズ、メーカー、エンジン、そして搭載される装備(航海計器や内装など)によって大きく変動します。
サイズ別・新艇価格の目安
-
エントリークラス(20~25フィート):
主にフィッシングやトーイングスポーツを目的とした比較的小型のボートです。価格帯としては、およそ500万円から1,500万円程度が一つの目安となります。自動車で言えば、高級セダンやSUVに近い価格帯です。
-
ミドルクラス(26~35フィート):
家族や友人とクルージングを楽しむのに適した、居住空間も考慮されたモデルです。価格は2,000万円から8,000万円程度まで幅広く、このクラスになると選択肢も一気に増えます。
-
ラグジュアリークラス(36フィート以上):
複数の個室や豪華な設備を備えた大型クルーザーです。価格は1億円を超えるものがほとんどで、まさに夢のスーパーヨットの世界が広がっています。
価格を左右するその他の要因
船の価格は、単純な大きさだけでは決まりません。例えば、エンジンを1基搭載するのか2基搭載するのか、国産メーカー(YAMAHA, TOYOTA, YANMARなど)なのか、あるいは海外の高級ブランド(Princess, Sunseeker, Ferrettiなど)なのかによっても価格は大きく変わります。
また、レーダーやGPSプロッターなどの航海計器、発電機やエアコンといった快適装備を追加していくと、オプション費用だけで数百万円以上になることも珍しくありません。新艇を購入する際は、艇体価格だけでなく、どのような装備が必要かを考え、総額で予算を組むことが求められます。
狙い目な中古艇の価格相場と選び方
新艇には手が届かないけれど、どうしても自分の船が欲しいという方にとって、中古艇は非常に魅力的な選択肢となります。中古市場に目を向ければ、同じ予算でもワンランク上のサイズのクルーザーを手に入れることが可能です。
中古艇の価格は、年式、使用状況(特にエンジンの稼働時間)、メンテナンス履歴、そして人気などによって大きく左右されます。一般的には、新艇価格の半額以下で購入できるケースも少なくありません。例えば、10年落ちの30フィートクラスの国産クルーザーが、1,000万円前後で取引されていることもあります。
しかし、価格の安さだけに惹かれて飛びつくのは危険です。中古艇は一艇一艇の状態が大きく異なるため、購入後の思わぬトラブルや高額な修理費を避けるためには、慎重な船選びが不可欠です。
中古艇選びで失敗しないためのチェックポイント
中古艇を選ぶ際には、少なくとも以下の点を確認することが大切です。
-
船体の状態:
船体はFRP(繊維強化プラスチック)で作られていることがほとんどです。大きな傷やひび割れ、修復の跡がないかを入念にチェックします。特に、水面下の船底部分は重要な確認箇所です。
-
エンジンの状態:
船の心臓部であるエンジンの状態は最も重要です。アワーメーター(総稼働時間)を確認するとともに、これまでのメンテナンス記録を見せてもらいましょう。エンジン始動時の音や排気の色、冷却水の出方なども確認したいポイントです。
-
デッキやキャビンの状態:
デッキがフワフワと浮いた感じがしないか、雨漏りの跡はないか、装備されている電気系統は正常に作動するかなど、細かく見ていく必要があります。
中古艇の購入に際しては、個人での判断が難しい部分も多いため、信頼できるマリーナや販売店に相談することをお勧めします。また、第三者の専門家であるサーベイヤー(鑑定人)に購入前の船体調査(インスペクション)を依頼することも、安心して購入するための有効な手段です。

小型船舶免許で乗れるクルーザーを持つということ


イメージ画像
|
所有のメリットとデメリットを徹底比較
自分のクルーザーを持つことは、多くの人にとって大きな夢です。しかし、その夢を実現する前に、所有に伴うメリットとデメリットの両方を冷静に比較検討することが、後悔のない選択につながります。
クルーザーを所有するメリット
-
究極のプライベート空間:
海上では、誰にも邪魔されることなく、家族や友人との特別な時間を過ごせます。日常の喧騒から離れ、心からリラックスできる時間は何物にも代えがたい魅力です。
-
時間と場所の自由:
天候さえ良ければ、思い立った時にいつでも好きな場所へ出航できます。お気に入りの釣りスポットや、静かな入り江を自分たちだけで満喫できるのは、オーナーならではの特権です。
-
趣味の世界が無限に広がる:
クルージングはもちろん、本格的な釣り、ウェイクボードやシュノーケリングといったマリンスポーツ、船上でのバーベキューなど、クルーザーが一台あるだけで遊びの可能性は無限に広がります。
クルーザーを所有するデメリット
-
高額な費用:
最大のデメリットは、やはり費用面です。船本体の購入費用だけでなく、後述する維持費も継続的にかかります。経済的な負担は決して小さくありません。
-
保管場所の問題:
クルーザーは自宅に置いておくわけにはいかず、マリーナなどに係留・保管する必要があります。都市部ではマリーナの空きが少ない、あるいは保管料が高額であるといった問題もあります。
-
メンテナンスの手間:
車以上に、船は定期的なメンテナンスが欠かせません。塩害やフジツボの付着を防ぐための船底塗装、エンジンの定期点検など、時間と手間、そして費用がかかります。
-
天候への依存:
せっかくの休日でも、天候が悪ければ海に出ることはできません。自然が相手の遊びであるため、計画通りにいかないことも多々あります。
クルーザーの所有は、ライフスタイルそのものを変える大きな決断です。これらのメリットとデメリットを十分に理解した上で、ご自身の状況と照らし合わせて判断することが求められます。
クルーザー所有後のリアルな年間維持費
クルーザーを購入する際、艇体の価格にばかり目が行きがちですが、本当に重要なのは購入後に継続してかかる「年間維持費」です。この維持費を把握しておかないと、「買ったはいいけど維持できない」という事態に陥りかねません。
年間の維持費は、船の大きさや保管場所によって大きく異なりますが、一般的には「艇体価格の約10%」が目安と言われています。例えば、1,000万円のクルーザーであれば、年間100万円程度の維持費がかかる計算です。
維持費の主な内訳
-
係留・保管料:
維持費の中で最も大きな割合を占めるのがマリーナなどに支払う保管料です。場所や設備、船のサイズによって異なり、年間で30万円から100万円以上かかることもあります。
-
保険料:
万が一の事故に備え、自賠責保険にあたる「船舶所有者賠償責任保険」への加入が一般的です。加えて、自分の船の損害をカバーする「船体保険」にも加入すると安心です。保険料は船の価値や補償内容によりますが、年間5万円から30万円程度が目安です。
-
メンテナンス費用:
船を安全で快適な状態に保つための費用です。年に一度のエンジンオイル交換、消耗部品の交換、船底に付着する貝や藻を取り除き、専用の塗料を塗る船底塗装作業などがあります。これらでおおよそ年間10万円から50万円以上は見ておく必要があります。
-
燃料代:
当然ながら、海に出れば燃料代がかかります。クルーザーのエンジンは燃費が良いとは言えず、エンジンの種類や大きさ、航行の仕方によって大きく消費量が異なります。
-
法定検査(JCI)費用:
車でいう車検のようなもので、国が定める定期的な検査を受ける義務があります。6年ごとの「定期検査」と、その間に行う「中間検査」があり、数万円の費用がかかります。
これらの費用を合計すると、比較的小さな25フィートクラスのボートでも、年間50万円から80万円程度の維持費が見込まれます。購入を検討する際は、このランニングコストを支払い続けられるか、慎重にシミュレーションすることが極めて大切です。
気軽に体験!2級船舶免許で乗れる船のレンタル
「自分の船を持つのはまだ早いかもしれない」「もっと気軽にクルージングを楽しみたい」という方には、レンタルボートという素晴らしい選択肢があります。免許さえあれば、高額な購入費用や維持費を心配することなく、必要な時にだけ船を借りて楽しむことができます。
現在、全国各地のマリーナでは、ビジター向けのレンタルボートや、会員制のボートクラブが充実しています。特に、ヤマハが全国展開する会員制マリンクラブ「シースタイル」は有名で、入会すれば全国約140ヶ所のホームマリーナで手軽にボートをレンタルできます。
レンタルボートのメリット
-
手軽さと経済性:
最大のメリットは、購入や維持にかかる莫大な費用が不要な点です。必要な時に利用料金を支払うだけで、クルーザーオーナー気分を味わえます。
-
メンテナンス不要:
面倒な清掃やメンテナンスは、すべてマリーナ側が行ってくれます。利用者はただ操船を楽しむことに集中できます。
-
様々な船を体験できる:
フィッシングに特化したボートや、クルージング向けの快適なボートなど、その日の目的やメンバーに合わせて様々な種類の船を選ぶことができます。
料金体系は、時間単位でのレンタルや1日チャーター、あるいは月会費制など様々です。2級免許でレンタルできる20~30フィートクラスのボートであれば、数時間の利用で2万円~5万円程度が相場です。まずはレンタルで経験を積み、自分のクルーザーライフのスタイルを見つけてから、将来的な購入を検討するのも賢い方法と言えるでしょう。
レンタルボートを利用する際の注意点
手軽で魅力的なレンタルボートですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。安全に楽しむためにも、事前にこれらのポイントをしっかり理解しておくことが重要です。
操船スキルと経験
免許を取得したばかりの初心者が、いきなり馴染みのない海域で大きな船を操船するのは、想像以上に難しいものです。多くのマリーナでは、初心者向けの安全講習や操船レッスンを用意しています。まずはそうした講習を受けてから、比較的小さなボートで、慣れた海域からスタートすることをお勧めします。自分のスキルを過信せず、段階的にステップアップしていく姿勢が大切です。
事前の予約と計画
特に気候の良い週末や連休は、レンタルボートの予約が殺到します。利用したい日が決まったら、できるだけ早めに予約を入れましょう。また、当日の天候や海の状況を必ず確認し、無理な出航は絶対に避けるべきです。出航前には、マリーナのスタッフから航行上の注意点や、その日の海のコンディションについてアドバイスをもらうと良いでしょう。
ルールと規約の遵守
レンタルボートには、マリーナごとに定められた航行区域や利用時間、禁止事項などのルールがあります。これらの規約を必ず守ってください。また、出航前には、船に備え付けられている法定備品(救命胴衣や信号紅炎など)の場所と使い方を確認することも、船長の義務です。
保険内容の確認
万が一の事故に備えて、レンタル料金に含まれる保険の補償内容を事前に確認しておくことも忘れてはなりません。対人・対物賠償の上限額や、船体保険の免責金額(自己負担額)などを把握しておくと、安心して利用することができます。
これらの注意点を守り、安全第一で行動することが、楽しいレンタルボート体験の鍵となります。
理想の小型船舶免許で乗れるクルーザーを見つけよう

イメージ画像
この記事では、小型船舶免許で乗れるクルーザーについて、様々な角度から解説してきました。最後に、理想の一艇を見つけ、充実したマリンライフを送るための重要なポイントをまとめます。

|
―記事のまとめ―
|
「小型船舶免許で乗れるクルーザー」関連のサイト
1. 国土交通省 / Japan Coast Guard (海上保安庁)
法律や制度に関する最も正確な情報源です。免許制度の正式な内容、安全基準、法改正などの一次情報を確認できます。
2. 日本海洋レジャー安全・振興協会 (JMRA)
小型船舶免許の試験機関であり、安全なマリンレジャーの普及を目的とした公益財団法人です。
3. 大手船舶メーカー
国内の主要な船舶メーカーの公式サイトは、実際にどのようなクルーザーが販売されているか、そのスペックや価格帯を知る上で非常に信頼性が高い情報源です。
|
|
―関連記事― |